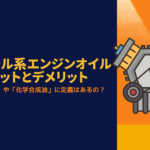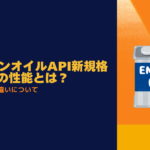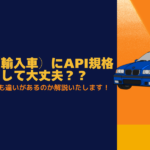長年愛車に乗っているとこのように感じられる方はいらっしゃいませんか?
- 燃費が依然と比べて落ちた
- パワー(馬力)が昔よりも出ない
- オイル漏れしまう・白煙・異音が出る
基本的には修理工場でパーツを交換することが一般的で確実ではありますが、修理の内容によっては日数がかかったり費用が高額になってしまい、敬遠しがちになる方もいらっしゃるかと思います。修理工場に預けられるまとまった時間が取れるまで、そのままにしておくわけにはいきませんよね。そのような場合でも上記のような不調の内容によってはご自身で改善できるものもあります。その方法とはずばり“専用のエンジンオイルに交換する事”です。
専用のエンジンオイルについてはこれから説明するとして、“え、エンジンオイルならきちんと交換しているよ?”“エンジンオイルで変わるとは思えない”と思われる方は多いかと思います。
もちろん原因にはよりますが、比較的低コストで改善できるのであれば試してみる価値はあるのではないかと筆者は考えます。今回は専用のエンジンオイルを交換することで改善する症状・修理に持っていくべき症状を原因毎に基礎知識から説明致します。
不調が出ている場合で、今使っているエンジンオイルが低粘度(メーカー指定など)である方は一度本記事をご確認いただければ幸いです。
※長めの記事になっていますので、あとから読み返される方はブックマークをお勧めします。
もくじ
エンジンオイルと燃費の関係
エンジンオイルと燃費には密接な関係があります。それにはエンジンの駆動の抵抗が関係しています。理由について1から見ていきましょう。
エンジンオイルの役割について
自動車が走行するための動力としてエンジンが存在します。エンジンは燃料を使って内部で高速ピストン運動を行っており、高熱かつ激しい摩擦が起きてしまう環境にあります。エンジンオイルはそのような状態を緩和し、エンジンを保護する大切なものなのです。エンジンオイルは大きく5つの役割があります。
潤滑性能(スムーズに動かす)
エンジン内部にあるパーツはピストン運動(上下運動)を繰り返すため、パーツ間に摩擦・摩耗が発生する環境にあります。エンジンオイルが油膜を形成することで緩衝剤となり、滑らかに動くことをサポート。エンジンの保護をします。
密封性能(隙間を埋める)
潤滑性能で説明した緩衝剤としての役割だけではなく、パーツ間の隙間を埋める役割も行います。隙間があると精製したエネルギーが漏れてしまい、100%の力がピストンリングに伝わらない為、エンジンオイルが密封の役割を果たします。
洗浄性能(状態を綺麗に保つ)
エンジンオイルが潤滑することによって内部に発生したスラッジ(エンジン内部に発生した燃えカス)や金属摩擦等を取り除き、エンジン内部を綺麗に保ちます。エンジンオイルが黒くなる理由の1つです。
冷却性能(高温負荷状態を軽減する)
エンジンが駆動するうちに燃焼や摩擦等で高温になります。エンジンオイルは熱を吸収し、オイルパン(エンジンオイルを溜めておく場所)に蓄積することで冷却され、再びエンジン内部を潤滑します。高温によってエンジンパワーが落ちることやエンジン部品が破損することを防ぎます。
防錆性能(錆の発生を防ぐ)
エンジン内部は燃焼や回転運動により高温になる関係上。外気との温度差により水分が発生する為、錆が発生しやすい状況になります。エンジン内部の部品に油膜を作ることで水分が直接触れることを防ぎ、錆が発生することを防ぎます。
燃費について
燃費とはガソリン(軽油)1Lあたり自動車が何km走行できるかを表した数字になります。調べ方としては以下の通りです。
- ガソリン(軽油)を満タンにする
- トリップメーター(スピードメーターにある距離計)をリセット
- 再度給油するタイミングでトリップメーターに表示されている距離と給油量を測定
- トリップメーターに表示されている距離(km)÷給油量(L)で燃費を計算
燃費の数字が高いほどエネルギー効率のいい自動車といえます。一般的にはガソリン車よりもディーゼル車の方が燃費が良い傾向にありますが、ハイブリッド車と呼ばれる電気モーターとエンジンを両立させた自動車も燃費が良い自動車として知られています。
エンジンが駆動する仕組みについて
エンジンにはガソリンを燃料とするガソリンエンジンと軽油を燃料とするディーゼルエンジンの大きく2種類が存在します。どちらも吸気→圧縮→燃焼→排気の4工程でエンジンは動きます。
- 吸気:ピストンが下がることで吸気バルブが開き、エンジン内のシリンダーに空気を取り入れる
- 圧縮:ピストンが上がることで、シリンダーに取り入れた空気と燃料を圧縮させる
- 燃焼:圧縮した状態で点火・燃焼させることで爆発を起こし、反動でピストンが下がる
- 排気:ピストンが上がることで、排気バルブが開き排ガスを出す
上記がエンジンが駆動する大まかな一連の仕組みになります。旧車は主にガソリンエンジンが多いかと思いますが、駆動方法が違うため2種類とも説明致します。
ガソリンエンジン
ガソリンを燃料とするエンジン。密閉された室内に、スパークプラグと呼ばれる点火装置で空気と混ざりあったガソリンに着火することで燃焼・小爆発を発生。爆発した圧でピストンリングへ力が伝わり駆動します。ディーゼルエンジンと比較して高回転で静かに回る点が特徴です。
ディーゼルエンジン
軽油を燃料とするエンジン。ピストンによって圧縮し高温になった空気が密閉された室内に溜まっており、霧状にした軽油を吹きかけることで軽油が自然発火を起こし、燃焼・小爆発を発生。爆発した圧でピストンリングへ力が伝わり駆動します。ガソリンエンジンと比較して燃費が良く低回転でも力強いトルクを発生させることができる点が特徴です。
ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンは駆動させる仕組み自体は違いますが、シリンダー内にあるピストンが上下運動することによって動力を伝えるという点では同じです。このピストン運動にかかる抵抗で燃費に影響がでるというわけです。
エンジンオイルの粘度と燃費の関係
一般的にエンジンオイルが低粘度であるほど抵抗が少ないため、燃費が良くなる傾向にあります。また、低温時に比べて高温時の方が粘度が低くなる性質上、始動時や冬季などでもよりスムーズなエンジンスタートを切ることができることがあげられます。ただし、条件によっては例外が存在します。
高粘度エンジンオイルの方が燃費が良くなる場合とは
先ほど低粘度は抵抗が少ないために燃費が良くなる傾向にあるとお伝えしましたが、それはエンジンの摩耗が進んでいない新しいエンジンに当てはまります。摩耗している過走行車や旧車のエンジンは、新車のエンジンに比べてクリアランスと呼ばれるシリンダーとピストンの間にある隙間が大きくなっています。そのため、低粘度のエンジンオイルでは密閉の機能が足りず、小爆発で発生した圧が抜けてしまうことで、精製したエネルギーが完全に伝わらなくなります。結果的にエネルギー効率が落ちてしまうため、燃費が下がってしまうことにつながります。粘度を上げることで、厚い油膜を精製し隙間をしっかりうめることができるため、燃費の改善につなげます。エンジンの状態に合わせたエンジンオイルを使用することが大切です。
エンジンオイル交換以外での燃費の改善方法とは
燃費が落ちる原因はエンジンの経年劣化だけではありません。エンジンオイルを適切な粘度に変更したとしても改善されない場合もあります。大半が部品交換になりますが、ご自身でできるものもありますのでお伝えします。
バッテリー(電気系統)の劣化・故障
バッテリーは電力を溜めておく電池の役割をしており、発電機(オルタネーター)が発電した電力を蓄える役割を担っています。発電機はエンジンが駆動している際に電力を生成する仕組みになっています。本来なら発電機とバッテリーの2軸で電力を供給するのですが、バッテリーが劣化することにより蓄える電力量が減り、発電機が常に高電力を生成する必要が出てしまいます。その結果エンジンの負担が増え、燃費の悪化につながります(特にアイドリングストップ付き車)。バッテリーが劣化した際はご自身もしくは修理工場で交換をしましょう。
タイヤの劣化
タイヤの劣化(空気圧の低下)も燃費悪化の原因の1つといえるでしょう。エンジンから駆動系へと伝わった力が100%発揮できなくなります。自転車でも空気が入っていないタイヤだと走行が大変なのと同じように燃費にも影響します。タイヤの交換などで対応できます。
スパークフラグの劣化
エンジンが燃料を発火し燃焼を起こすために使われる発火装置です。スパークプラグが劣化すると燃焼が弱まり、本来よりもパワーが落ちてしまいます。そのため、同じパワーを出すために結果的に燃費が落ちてしまうことにつながります。スパークフラグが原因の場合は修理工場に持っていきましょう。
センサー類の故障
エンジンが燃焼を起こす際に適切な量の燃料を調整するためのセンサーです。センサーが故障すると過剰に燃料を使用し、燃費悪化につながります。エンジン警告灯が点灯する理由の一つでもあります。その際は修理工場に持っていきましょう。
車両に積んでいる荷重量
車両の重量が重いとその分馬力が必要になります。不要なものはできるだけのせないようにすることで燃費が改善されるかもしれません。
エンジンオイルとエンジンパワー(馬力)の関係
長年愛車に乗り続け、走行距離が増えるとエンジンパワー(馬力)が落ちたと感じることもあるかと思います。エンジンオイルも関係しているため、この理由について1からわかりやすくご説明します。
馬力とトルクについて
馬力とは、エンジンが生み出した力で自動車がどれくらい動くかという仕事量を表したもので、単位をWで表記して数字で表されます。
トルクとは、エンジンの燃焼室内で爆発して発生した1回あたりの力のことを表したもので、加速力を意味します。
馬力は以下の様に表されます。
馬力(エンジンパワー)=トルク(加速力)x回転数
上記の内容だとイメージがしづらいかと思いますので、よく例えられる自転車が動く仕組みと新たに階段を上がる仕組みの2例をあげましょう。
自転車の例
自転車をこぐためにはペダルを下方向に力を加えるかと思います。この力がいわゆる自動車のトルクと呼ばれるもので、力を加えた分より加速します。ペダルをこぐとペダルにつながっているクランク(ギア)が回転しますが、これが上記の式にある回転数に当たります。
自転車の変則ギアで考えてみましょう。ギアを軽くした場合、ペダルに加える力(トルク)は小さくて済みますが、その分ペダルをこぐ回数(回転数)を多くしないと進みません。ギアを重くした場合、ペダルに加える力(トルク)は必要になりますが、ペダルをこぐ回数(回転数)は少なくても進みます。この2つの要素を掛け合わせたものが走行力(馬力)に反映されるというという理論になります。
階段の例
階段を上がる動作でも同じように例えることができますね。同じ階段を一段ずつと二段ずつ(一段飛ばし)登ると仮定しましょう。一段ずつ上がる方が登るためにつかう力(トルク)は少なくて済みますが、登る段数(回転数)はその分多くなります。二段ずつ(一段飛ばし)だと、登るために使う力(トルク)は2倍必要ですが、登る段数(回転数)は半分で済みます。この二つを掛け合わせたのが登った距離(馬力)になります。
つまり、トルク・回転数が落ちると馬力も落ちるということになります。
自動車によってトルクの大きさや最大トルクが発生する回転数が異なってくるため単純なものではありませんが、理論上は上記の仕組みになります。
旧車・過走行車の馬力が落ちる理由
馬力がおちる理由はいくつか考えられますが、主に各パーツの経年劣化によります。考えられる理由は以下の通りです。
エアクリーナーの汚れ
エアクリーナーの詰まりによりエンジンの回転に必要な空気量が足りず、加速ができなくなります。クリーナーの清掃や交換を行うことで解決します。
点火系の異常
イグニッションコイルやプラグの異常により点火不良になることで、馬力が落ちることがあります。イグニッションコイルなどの交換が必要になる場合があります。
燃料系の異常
燃料ポンプやインジェクターの不具合・汚れにより燃料供給が不足するために、馬力が落ちることがあります。インジェクションクリーナーなどの添加剤等で対応、改善が見込めなかった場合は整備工場に点検してもらいましょう。
オーバーヒート
オーバーヒートとは、エンジンから発生する熱量がエンジンの冷却性能を越え、高温状態での稼働が続くことでエンジンの性能が落ちてしまうことです。そのため、エンジンパワーも落ちてしまいます。エンジンオイルやクーラントなどの交換及び整備工場に点検してもらいましょう。
エンジンの摩耗
エンジンオイルと燃費の関係の項目の“低粘度であればあるほど燃費が良くなるとは限らない”で詳しく説明しましたが、エンジンが摩耗すると低粘度エンジンオイルでは精製したエネルギーが抜けてしまう可能性があります。結果的に馬力が落ちてしまう原因になるため、自動車に合わせたエンジンオイルの選択が必要です。
エンジンオイルの粘度を上げることでエンジンパワー(馬力)は上がるのか?
先に結論からお伝えすると上がる可能性・下がる可能性どちらもあります。というのも、馬力が落ちている原因が自動車によって異なるからです。前提として、高粘度の方が粘度抵抗が高いため、馬力は落ちる傾向にあります。ただ、旧車・過走行車に関しては上記の馬力が落ちる理由に当たる“エンジンの摩耗”の観点から、エネルギー漏れを防ぎエンジンパワーが上げることができます。馬力が落ちる理由は様々ありますが、高粘度の専用エンジンオイルを使用することはエンジンパワー復活にむけた試す価値のある一つの対策であるといえるでしょう。
エンジンオイルとオイル漏れ(白煙・異音)の関係
オイル漏れは旧車・過走行車では発生しがちな問題です。白煙や異音はオイル漏れが原因としてがあげられます。オイル漏れといっても外漏れと内漏れの2種類あります。順にみていきましょう。
エンジンオイルの外漏れとは
外漏れとは駐車中の車の下に液体が漏れ出る現象のことです。液体は様々な可能性がありますが、エンジンオイルの特徴としては黒く、焦げた臭いがします。引火の可能性もあるので、取り扱いには注意が必要です。赤や緑だとクーラント液の可能性があります。
外漏れの原因と対策
理由はいくつか考えられますので、順にみていきましょう。
オイルパッキンやオイルシールなどの劣化
エンジンオイル交換を下抜きでする際にドレンボルトと呼ばれるボルト状のものを外してエンジンオイルを抜きますが、そこから漏れている可能性があります。具体的にはオイルパッキンなどの劣化があげられます。また、最近の自動車は問題ないですが、旧車だと合成油がオイルシールを収縮させてしまう可能性もあるため、外漏れにつながることもあります。最も多い外漏れの原因ですが、交換自体は安価かつオイル交換の際に変えるだけなので、個人でもメンテナンスしやすい箇所といえるでしょう。
ドレンボルトやオイルパンの摩耗
エンジンオイルを溜めるためのオイルパンについているドレンボルトが走行中などによる振動が蓄積して緩んでしまうことで、オイル漏れを引き起こす可能性があります。なかには、ドレンボルトが摩耗したり、オイルパン自体が飛び石などでダメージを受ける・錆などにより腐食することで外漏れすることも可能性としてあります。その際は近くの整備工場に持ち込み、交換などの修理をしてもらいましょう。
エンジンオイルの中漏れとは
車体からエンジンオイルなどの液体が漏れるなど症状のわかりやすい外漏れとは異なり、エンジン内部の燃焼室に本来入るはずのないエンジンオイルが漏れだしてしまい、燃料とともに燃えてしまう現象のことです。その結果、マフラーから白煙・異音が発生するなどの影響が出ます。エンジンの駆動中(吸気→圧縮→燃焼→排気)に発生し、燃焼室への入り方や過程によって“オイル上がり”と“オイル下がり”の2つの現象に分かれます。
オイル上がりとは
エンジンが駆動する方法は、上記の“エンジンが駆動する仕組みについて”で説明したシリンダー内にあるピストンが上下運動をすることによってなのですが、摩耗することによってピストンとシリンダーの間にある隙間(クリアランス)が大きくなります。その結果、本来入るはずのない燃焼室へオイルが上がってきてしまう事をオイル上がりといいます。
この性質から、圧縮から燃焼が起こりピストン回転数が多くなる、つまり加速時に白煙が発生する場合はオイル上がりの可能性があります。
オイル上がりの原因と対策
エンジンオイルの油膜の形成が足りずクリアランスが大きいために、燃焼室にエンジンオイルが入り込んでしまっていることがあげられます。そのため、高粘度エンジンオイルにより油膜を厚くすることで、オイル上がり(白煙・異音)を防止できる可能性があります。
オイル下がりとは
吸気及び排気のタイミングでそれぞれ開くバルブ(弁)がありますが、そこからエンジンオイルが燃焼室に入ることをオイル下がりといいます。
オイル上がりとタイミングが異なり、始動時や減速時でも白煙・異音が出る場合はオイル下がりの可能性があります。
オイル下がりの原因と対策
吸気バルブ及び排気バルブも度重なる開閉により摩耗してしまいます。それを防ぐ為にバルブシールと呼ばれる部品が緩衝材の役割をしているのですが、バルブシールが劣化することでオイル下がりが発生している可能性があります。オイル下がりと思った際は修理工場で見てもらいましょう。
エンジンオイル交換で対策できる事まとめ
今回は旧車・過走行車にありがちな3つの問題でエンジンオイル交換で対応できるものについてご説明しました。まとめると、高粘度のエンジンオイルに交換することで不調が収まる可能性があるものは以下の通りです。
- 燃費性能
- エンジンパワー(馬力)
- エンジンオイルの外漏れ
- 白煙・異音(オイル上がり)
エンジンが関連する問題では高粘度エンジンオイルへの交換が効果的になる可能性があるといえるでしょう。
JDAでは40番や50番の粘度など高粘度のエンジンオイルも豊富に取り揃えております。

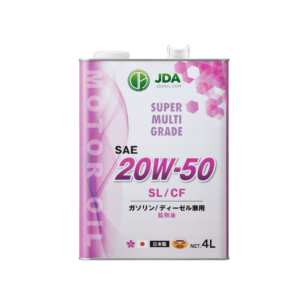
もし上記のような不調でお困りでしたら、ぜひお試しいただき効果を実感頂けると幸いです!
日本発の中古車輸出企業からスタート。30ヶ国以上で実績を積み高品質な自動車部品の自社開発も手がけます。エンジンオイル・ブレーキパッド・オイルフィルター・エアフィルター等、こだわりのMADE IN JAPANを世界中へ届けています。