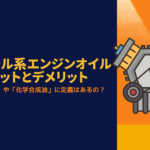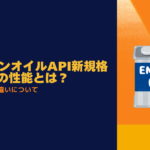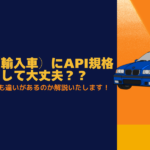皆様は年間でどれくらい交通事故が起きているかご存じでしょうか?交通事故総合分析センターによりますと、2024年度の交通事故発生件数は290,895件(うち死亡事故件数は2,598件)と1日で約800件発生しています。このように聞くとかなり多いと感じませんか?事故にも様々原因があり、人為的ミスによる事故もあれば、自動車の機材トラブルによる事故もあります。少なくとも機材トラブルに関しては事前のメンテナンスで事故を大きく回避できる内容です。
自動車学校を出た人は、教習前自動車に乗るときに自動車の周りやライトがつくかなど、様々なことを確認したかと思います。それに加えて自動車学校では習わなかった自動車自体のメンテナンス方法について触れていきます。
最悪の事態を防ぐためにも、今回は誰でも簡単にチェックできる内容を3点お伝えします。万が一不良が確認された際は整備工場などに修理を依頼しましょう!
もくじ
まず初めに
メンテナンスというととても大変なものに感じるかもしれません。しかし内容によっては簡単に終わるものもあります。ご自身でできるものはコスト削減でご自身で、複雑なものは整備工場やカーショップなどに頼むなど、うまく使い分けていけばいいと思います!わからないことがあれば、プロに実際に確認しに行きましょう。
メンテナンスをするうえで、ボンネットを開ける必要があるものは多数あります。そのため、ボンネットの開け方からお伝えします。
ボンネットの開け方
①ボンネットを開けるためにはまず開けるためのボタンがあります。一般的に運転席右側足付近にあります。

②ボンネットが半開きになったら前方へ行き、中央部分を確認します。
③中央裏側にフックがあるのでそのフックを押しながら持ち上げます。熱くなってる可能性があるので、手袋なり充分確認したうえで作業を行いましょう。


④サイドにボンネットを支えるつっかえ棒があるので、ボンネット裏にある穴に差し込んで固定します。

以上でボンネット内側を確認できます。
ライトの確認!
夜間を走行する時は必ずライトをつけますよね。ライトをつけないと走行中に前方の視界が悪くなる他、歩行者や対向からくる車両視点からも自動車の認識ができず、事故につながってしまいます。危険ですので、必ずライトがつくか確認しましょう!


ライトがつかない場合
ライトがつかなかった場合、原因はいくつか考えられます。今回は代表的なものを紹介します。
電球が切れている
全体ではなく、1か所電球が切れている場合は電球の寿命が来てしまった可能性があります。他の電球も寿命が近い可能性が高いため、まとめて交換しておきましょう。
バッテリーが切れている
バッテリーの寿命は約3年ほどですが、全体のライトがつかない場合はバッテリーが弱まっている可能性があります。
また、以下の場合はエンジンが始動できなくなる、バッテリー上がりを起こしてしまいます。
・駐車した後にライトを消さずに買い物にでかける
・ドアが完全に閉まっておらずルームライトがついたまま放置する
よくある一例として、昼間にトンネル内でライトをつけたまま消し忘れてしまい、駐車しても明るい為にライトがついていることに気付かなかったケースです。
自動車に乗りなれている方も意外とやってしまいがちな問題ですが、バッテリーの劣化が早まる原因になるので注意しましょう。
バッテリーの確認の仕方
①バッテリーは自動車前方にあります。まずはボンネットを開けましょう。※エンジンが十分に冷えてから作業しましょう。
②バッテリー液の残量がLOWER(下限)とUPPER(上限)の間にあるか確認します。
劣化していると感じたら、ご自身で交換もしくはカーショップで交換してもらいましょう。
エンジンの確認!
エンジンは自動車の心臓です。エンジンに問題が起きると、一気に重大な事故につながります。特に遠出をする際は必ず確認するようにしましょう。
エンジンオイルの交換
エンジンオイルとは、エンジンが最高の状態で駆動するために重要なサポートを行う大切なもので、よく人間の血液に例えられます。エンジンオイルが足りない・劣化した状態で走行すると、エンジンが摩耗してしまい、壊れてしまいます。エンジンが壊れた車は基本的に廃車になります(エンジン交換費用が高額で、新しく買い替えるのと変わらないため)。エンジンオイルは自動車のメンテナンスで最も頻繁に交換するものです。エンジンオイルがしっかり入っているか、劣化していないか、事前に確認しておきましょう。
エンジンオイルの確認の仕方
①エンジンは自動車前方にあります。まずはボンネットを開けましょう。※エンジンが十分に冷えてから作業しましょう。
②オイルレベルゲージを抜きます。抜くのに力がいる時があります。
③引き抜いたら、ウエスやタオルなどで一度エンジンオイルをふき取ります。

④再度根元までしっかりさしたのちに引き抜きます。オイルレベルゲージの先端をみて、オイルの色(黒くなっていないか)や量(先端にある印の中に納まっているか)を確認し、必要があれば交換しましょう。
クーラント(ラジエーター液)の交換
クーラントとは、エンジンを冷やし熱を防ぐための液体です。通常の水と異なり、0℃未満でも凍らず、錆にくい特性があります。そのため、水道水で代用するのは控えましょう。クーラントにもLLC(ロングライフクーラント)と呼ばれる2~3年の交換周期のものもあれば、SLLC(スーパーロングライフクーラント)と呼ばれる7~10年持つものもあります。比較的交換頻度が少ないものではありますが、エンジンの故障をおこさないためにも、しっかりと確認しましょう。
クーラントの確認の仕方
①ラジエーターは自動車前方にあります。まずはボンネットを開けましょう。※エンジンが十分に冷えてから作業しましょう。
②クーラント液の色(薄黒くなっていないか)や残量(横にあるメモリ内に収まっているか)確認する。
タイヤの確認!
タイヤは、自動車が動くために直接作用している唯一のパーツです。車体自体に加えて、乗員・荷物などの重量を支えつつ、車体のバランスをとる重要な役割を担っています。走行中にタイヤに不良があった場合、大事故に直結します。必ず確認しておきましょう!タイヤは4つとも摩耗していくため、交換する際は全てのタイヤを交換してきましょう。
タイヤの状態を見るために確認する場所
タイヤを確認するといっても具体的にどこを確認するのかわからない方も多いかと思いますので、実際に確認する場所をお伝えします。
タイヤの溝や摩耗
タイヤの溝がしっかりと残っているか、摩耗していないかを確認します。タイヤの溝が浅いと事故につながる可能性があります。自動車学校でハイドロプレーニング現象という名前を聞いたことがあるかと思います。ハイドロプレーニング現象は主に雨天時の高速道路走行中に発生し、タイヤと路面の間に発生する水膜の影響でタイヤが浮き上がることで、ハンドルやブレーキか効かなくなる現象のことです。そのため、タイヤと路面の間に発生する水膜を防ぎ、水をかきだすためにタイヤの溝が必要なのです。
確認方法
①タイヤにある三角形の形をしたマーク(スリップサイン)を探します。

②三角形の先の延長線上の溝を確認します。溝がすり減ってなく並行になってしまっていると、滑りやすい状態のため交換が必要です。

タイヤの空気圧について
タイヤに空気がはいっていないと、タイヤの摩耗が激しくなり、走行時の安定性が損なわれる可能性があります。そのため、事前に適正な空気圧にしておく必要があります。
確認方法
自動車によって場所は異なりますが、主に運転席側のドアを開けたところに適正空気圧がかかれたシールが貼られています。それを基に空気圧を調整します。
ご自身で実施する場合はエアゲージとエアコンプレッサーが必要になります。お持ちでない場合はガソリンスタンドやカーショップなどで対応してもらえるため、旅行前に燃料補給がてらチェックしてもらいましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。今回は誰でも1分でチェックできる項目についてご説明しましたが、他にもより快適に運転するうえで確認したい箇所はいくつかあります。まずは簡単なものから始めていき、自動車メンテナンスについて慣れ親しんでいただければと思います。
日本発の中古車輸出企業からスタート。30ヶ国以上で実績を積み高品質な自動車部品の自社開発も手がけます。エンジンオイル・ブレーキパッド・オイルフィルター・エアフィルター等、こだわりのMADE IN JAPANを世界中へ届けています。