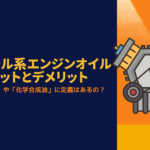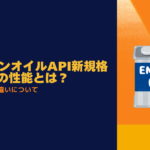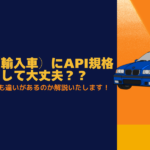近年自動車業界は電気自動車しかりハイブリッドしかり、目まぐるしく進歩が進んでいます。そのなかで自動車が年々新モデルが発売されるように、エンジンオイルも新モデルが発売されるのをご存じでしょうか。2025年4月より、日本で主流のAPI規格と呼ばれる規格の最新規格であるSQがリリースされました。JDAではすでに0W-20をSQ/GF-7Aでご提供しています。今回はSQ規格についてどういったものであるのか徹底解剖していきたいと思います!
もくじ
API規格とは
アメリカ石油協会(American Petroleum Institute)がエンジンオイルの品質を定めた規格(基準)です。日本の各自動車メーカーはAPI規格を指定しており、日本で主流の規格になっています。
ガソリンエンジン用オイルはS+アルファベット1文字で表記され、2025年9月現在「SA」~「SQ」までの規格に分けられます。API規格は数年ごとにSの次のアルファベットを1つ進めた表記の新規格がリリースされます。
なお、SQ規格の後ろにあるGF-7はILSAC規格と呼ばれるもので、API規格の中で省燃費性の項目について定められた規格です。
0W-16 GF-7B
0W-20 GF-7A
5W-30 GF-7
それ以降の粘度についてはILSAC規格に対応していません。
規格が更新される理由
エンジンオイルの規格が更新される理由は、大きく以下の2つがあげられます。
・既存性能の向上
・新しい性能基準の追加
基本的に新規格は前規格の性能を維持しつつ、社会情勢に合わせて近代的な性能に対応したものになります。
最近の規格更新における代表的な例がハイブリッド車でしょうか。
ハイブリッド車とはガソリンエンジンと電気モーターの2つを動力源とした自動車です。ガソリンが有限資源であること、大気汚染による環境問題の対策が必要であることが大きな理由となり開発されました。環境問題に対応していく中で、エンジンオイルもハイブリッド車などの環境対策された自動車にあわせた性能が必要になっていきました。このような背景から、省燃費性能は規格が更新されるにつれて向上しています。
SQ規格の特徴
先ほど新規格は前規格の性能を維持しつつ、社会情勢に合わせて近代的な性能に対応したものとお伝えしましたが、新規格SQは前規格SPと比較してどのように変わったのでしょうか。
実は7項目も既存性能が向上もしくは性能基準が追加されているんです。
分けると以下の通りになります
【既存性能の向上】
・高温酸化安定性
・省燃費性・省燃費持続性の向上
・タイミングチェーンの耐摩耗性の向上
・MRV試験の低粘度化(60000cP→40000cP)低温粘度特性
【性能基準の追加】
・使用油のLSPI防止性能の追加
・硫酸灰分試験の追加 触媒適合性
・新しいシール材の適合性の追加
簡単に1つずつ見ていきましょう。
既存性能の向上
既存性能の向上に関しては4点あげられます。
高温酸化安定性
エンジンオイルは90℃前後が適温といわれていますが、それ以上の高温になると劣化しやすくなります。このような状況が続くと、エンジンオイルの酸化や、ピストンデポジットと呼ばれる、燃え残りが原因でエンジンピストンにカーボン(炭素)が蓄積することにつながります。結果的にエンジンオイルの粘度や潤滑機能の低下につながり、エンジンにダメージを与えてしまいます。
SQ規格では、SP規格に比べて9.5%ほど高温酸化安定性の基準が向上しました。これにより、エンジンオイルの耐久性がさらに上がりました。
省燃費性・省燃費持続性の向上
燃費について意識している方は多いのではないでしょうか。燃費について簡単にお伝えすると、ガソリン(軽油)1Lあたり自動車が何km走行できるかを表した数字です。燃費の数字が高いほどエネルギー効率の良い(省燃費)自動車といえます。環境問題の対策として省燃費があげられている昨今、エンジンオイルもより省燃費に向けて研究がすすめられました。
SQ規格では、SP規格に比べて0.2%~0.5%ほど燃費性能の基準が向上されました。これにより、さらに燃料費削減に貢献します。
タイミングチェーンの耐摩耗性の向上
タイミングチェーンとは主にエンジンの始動に関係するパーツです。タイミングチェーンが摩耗すると、エンジンに負担を与えてしまいます。交換頻度が少ないパーツゆえに交換工程が大変で、交換になった際は高額な費用が掛かります。
SP規格からタイミングチェーンについての摩耗防止基準が追加されました。
SQ規格では、SP規格に比べて6%ほど摩耗防止性能の基準が向上しました。これにより、より長く愛車に乗れるようになりました。
始動性の向上(低温時流動性の向上)
エンジンオイルは低温であればあるほど固く、高温になればなるほど粘度が柔らかくなります。粘度が固ければその分抵抗も大きくなるわけですが、エンジン始動時がその状態に当てはまります。エンジンオイルの適温は90℃前後ですので、始動時はエンジンオイルの性能が発揮しづらい状態なのです。特に冬場はエンジンオイルの温度も低く、エンジン全体にいきわたりづらくなるため、燃費に影響します。これが続くと、エンジンオイルがマヨネーズのような形に固まっていくゲル化を引き起こしてしまいます。
SQ規格では、SP規格に比べて33%ほど始動性の基準が向上しました。これにより、より快適に自動車を始動できるようになりました。
性能基準の追加
性能基準の追加に関しては3点あげられます。
使用油のLSPI防止性能の追加
LSPIとはLow Speed Pre Ignitionの略で、低速早期着火と呼ばれる異常燃焼現象です。エンジンは燃料を燃焼してエネルギーを生成することで駆動します。LSPI現象は燃料を点火する際に、通常の点火タイミングよりも早く燃料が自然発火してしまう現象で、エンジンにとって想定外の状況になります。そのため、エンジンノッキング(エンジンの騒音・振動)や不完全燃焼を起こし、エンジンへのダメージにつながってしまうことが大きな問題となっています。LSPIが起きる原因は様々ありますが、エンジンオイルに含まれている添加剤が影響していることがあります。
SP規格から新油の状態でのLSPI現象に対応する基準が設けられました。
SQ規格では、新油の状態だけではなく、新たに使用油(125時間使用後オイル)の状態でも新油と同等の基準が設けられました(一定時間での平均発生回数5回、最大8回まで)。これにより、よりエンジンに優しいエンジンオイルになりました。
硫酸灰分試験の追加
これは、排ガスから発生するススを減らすためにできた項目です。環境問題対策の1つである排ガス規制に対応するために、GPF(Gasoline Particulate Filter)もしくはDPF(Diesel Particulate Filter)とよばれる、排出されるススを減らすフィルターが近年自動車に取り付けられています。フィルターで排出を抑えたススはどんどん溜まっていくため、フィルターは詰まっていきます。フィルターが詰まると、燃費の悪化やエンジンの主力低下につながり、最終的にエンジンが止まってしまいます。GPF問題はヨーロッパなどではすでに基準が設けられていましたが、近年国土交通省HPでも取り上げられ、日本でも関心が深まっている内容です。
 SPまでは対策がされていませんでしたが、SQから燃焼後に発生する無機成分量を0.9%まで減らす基準が設けられました。これにより、環境にやさしいエンジンオイルになりました。
SPまでは対策がされていませんでしたが、SQから燃焼後に発生する無機成分量を0.9%まで減らす基準が設けられました。これにより、環境にやさしいエンジンオイルになりました。
シール材の適合性の追加
化学合成油はシールが伸縮し、特に旧車にはオイル漏れをおこしやすいという話を聞いたことがある人もいるかと思います。現在はシール素材も変わっていき、オイル漏れも起こりづらくなっていますが、劣化や年式によってはオイル漏れが発生してしまうこともあります。
SPでは5種類のシール材に対応していますが、SQから新たに4種類のシール材に対応、合計9種類のシール材に適合するようになりました。そのため、オイル漏れが起こしづらくなりました。
最新のSQ規格を試してみたいという方に向けて
2025年9月現在、海外を中心に徐々にSQ規格のエンジンオイルが増えてきています。JDAでは0W-20 SQ/GF-7Aをいち早くご提供しており、より快適なドライブライフの手助けになることを念頭にご提供させていただいております。
0W-20ならではの始動性に加え、高温時でも粘度が柔らかくなりすぎない安定した粘度維持力。低粘度で懸念されている長期的なエンジン保護性能をより向上させつつも、燃費性能をあげたスペシャルな商品になっています。この機会にぜひ一度お試しくださいませ。
API規格:SQ/GF-7A
SAE規格:0W-20
ベースオイル:全合成油
販売サイズ:4L/4Lx2
まとめ
いかがだったでしょうか。複数の方面でより性能が向上したAPI規格SQ。エンジンオイルもここまで進化したかといえる内容です。短期目線では違いが分かりづらくても、長期的にみて愛車を長く乗り続けたい方はぜひ試してみてください!
日本発の中古車輸出企業からスタート。30ヶ国以上で実績を積み高品質な自動車部品の自社開発も手がけます。エンジンオイル・ブレーキパッド・オイルフィルター・エアフィルター等、こだわりのMADE IN JAPANを世界中へ届けています。